2025.04.07
住宅を建築するときの儀式とは? 第二弾「上棟式」についてご紹介!!
こんにちは!スタッフの北川です。
北海道も、「もうすぐ春だよ!」と思わせてくれる日が続いております。
雪もほぼなくなってきました。
皆さんのお住いのところはいかがでしょうか?
息子も春休みが終わり、間もなく新学年のスタートです!
今年はクラス替えがあるのでドキドキしているみたいですよ( *´艸`)
西日本や東日本は満開ラッシュだそうです。桜前線は今週中に東北南部へ
ということで、今日は「サクラ」の豆知識を少しだけご紹介いたします!!
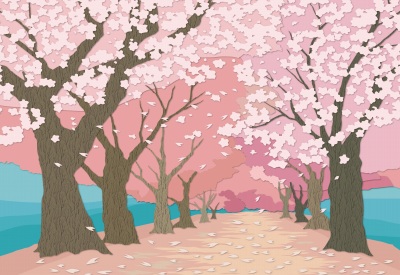
「サクラ」は日本列島を鮮やかに染め上げる、日本の春を象徴する存在です。
桜前線の終着点は、「北海道の根室」です。
「サクラ」はバラ科の植物で、その品種は600種類以上あります。
実は日本で見ることのできる「サクラ」のおよそ80%が「ソメイヨシノ」という品種です。
2月頃から咲き始め、多くは3月中旬から5月にかけて見頃を迎えます。
「サクラ」といえばピンク色の花のイメージですが、黄色や緑色の花を咲かせる品種もあるんです。
「サクラの花ことば」は、「高潔」「優れた美人」です。
満開に咲く優雅な美しさ、散り際の潔さ、表面的な美麗さだけでなく、凛とした強さを感じさせることから
このような花言葉がつけられたとされています。
今から、お花見が楽しみですね(^O^)/
家族、友人、会社の方を誘ってお花見にお出かけしてみてはいかがですか?
それでは、本題に入りましょう!!
前々回、住宅を建築するときの儀式として「地鎮祭」についてご紹介しました。
第二弾の今回は、「上棟式」です。
皆さん上棟式は御存じでしょうか?
聞いたことがあるけど、どんなことをするの?と思っている方もいらっしゃると思います。
そこで、今回は「上棟式」の意味や内容、具体的な進め方、費用など詳しくご紹介します。
おうちを立てようとお考えの方はぜひご覧ください(^O^)/

★上棟式とは・・・?
主に木造住宅を建築する際に、建物の骨組みまで完成したことを祝う儀式です。
タイミングとしては、完全に工事が終わるまでの途中工程でおこなわれます。
工事関係者への労いや感謝、これから完成にむけて工事がうまくいくように
祈願する意味を込めて行われます。
最近は神主を呼ばずに棟梁に仕切ってもらうのが、近年の一般的なケースです。
★上棟式のやりかた、流れは・・・?
今回は神主さんに来てもらうのではなく、簡略的に勧めるパターンをご紹介します。

①棟梁が、飾り物「幣串(魔除けの飾り)」を設置する。
②祭壇に御幣(ごへい)や神饌物(しんせんぶつ)などの捧げものを供える。
③四方固めの儀を行う:施主と棟梁が、家の四隅の柱に、酒・塩・お米・水などをまいて清める。
④工事が無事進むよう祈願し、二礼二拍手一礼する。
⑤直会(なおらい)の儀を行う:施主が挨拶をして乾杯をする。
⑥棟梁や関係者が挨拶する。
⑦場合によっては餅や銭、お菓子などをまく。
⑧手締めで式を締める。
⑨施主から棟梁や関係者にご祝儀や引き出物を配る。

地域や風習などによって内容は変わりますが、これが上棟式の大まかな流れになります。
★上棟式の服装は?
上棟式における服装に特に決まりはありません。
フォーマルな服装が一般的ですが、簡略的な上棟式の場合は、カジュアルは服装で参加する方も増えています。
関係者の方々に失礼のないように清潔感のある服装をおすすめいたします。
★上棟式はしないとだめなの?
上棟式は必ずするものではないため、上棟式をしないのも選択肢の一つです。
上棟式は縁起担ぎの要素が強いため、あまり気にしない方も多くいます。
いかがでしたでしょうか?
上棟式は、ただの新築を建てる中での作業ではなく大工さんたちと
コミュニケーションをとるための良い機会となります。
自分の家を建てるために頑張ってくれている大工さんたちを労うために、
上棟式ほどかしこまった式でなくとも、差し入れなどをして
感謝の気持ちを伝えるのも良いと思います。
新築時にしかできないことでもあるため、予算に余裕がある方は
前向きに検討してみてはいかがでしょうか?

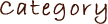


 Skogスタッフ(107)
Skogスタッフ(107)
 濱谷昭子(10)
濱谷昭子(10)
 北川聡美(202)
北川聡美(202)

